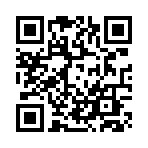2013年11月04日
悲しむということ 映画 「朝日のあたる家」をご覧になった方の感想
悲しむということ ~映画 「朝日のあたる家」~
わたしは10年ほど前に両親を相次いで亡くしました。
あまりにも悲しい出来事であったはずなのに、なぜか想像をしていた程泣けなかったのです。
きっとまだ緊張が続いているのだ、疲れているのだと自己分析しながらも、
次第に 、このままでは精神的に参ってしまうのではないかという不安感に襲われ、
もともと興味を持っていた精神世界へ足を踏み入れていきました。
それがヨガでした。
学んでゆくにつれ、明るい光を求め始めたのですが、
どん底に突き落とされるような感覚に何度も陥りました。
その辺りだと思います。
両親が本当にこの世にいないのだと思えるようになったのは。
「あぁ、話したいなぁ」と思っては、胃の辺りがキュっとなる苦しい淋しさを味わえるようになったのは...
そして、やっと両親への感謝の気持ちがわいてきたのです。
光を探すには暗闇が必要だと知りました。
わたしは両親の死を受け入れてはいなかったから、泣くことができなかったのです。
当たり前のことをもっともらしく書いていて、なんとも滑稽ですが、
悲しみを、ありのまま受け入れるということほど、私たちが不得意としているものはないかもしれないと
原発事故以降は特に実感しています。それは今も継続中ですが...
もともとチェルノブイリ原発事故に恐怖を抱いた青春時代があったので
それがこの日本で起こったことを知った瞬間は、頭が真っ白になりました。
しかし、周囲はまるでのんきに過ごしているようにみえ、
「テレビでそんなに言ってないから、大丈夫なんでしょ?」という反応を聞く度に
得体のしれない恐怖がわいてきて、孤独感を募らせる毎日でした。
それからは周囲の方が、わたしを遠巻きにするほど様々な情報を得ることに必死になっていました。
つのりゆく政府の対応への不信感、この世の中の、世界の原発構造への憤り、、、
そして、、、もちろん、福島の方々への想像をできる限りめぐらせてきたつもりです。
しかし、それは甘かった。
映画「朝日のあたる家」の冒頭から、わたしは終始泣き通しでした。
こんなに泣いたことはないです。
様々な種類の涙でした。
実はわたしは「泣ける映画」と謳った映画には全く興味がありません。
それほど「泣かされる」ことが嫌いなのです。
この映画は、泣かそうと工夫された場面はおそらくどこにもないのです。
ただただ淡々と、原発事故のあの日から起こった出来事が描かれているだけですから。
しかし、わたしは涙が止まりませんでした。
そしてそれは想像をしてもしきれない、私たちが味わったことのない
全く違った種類の「悲しみ」だと感じました。
この国は、いったいどこへ行こうとしているのだろうと思います。
「悲しみ」を置き去りにして。
光が暗闇の中でしか見いだせないとしたら、
私たちは、まず、この暗闇を見つめなければならないと思います。
きちんと悲しむことをしなければ、先へ進めないと思うのです。
いや、進んではいけないと思います。
映画冒頭に映し出された富士山に、わたしは突然涙が溢れました。
その切ないほど優雅で美しい姿に、心の底から申し訳ない気持ちになりました。
そして、なぜか「さようなら」という言葉が浮かびました。
日本語の「さようなら」は、
「さようであるならば」(そうならなければならないならば)というのが語源といいます。
これまでの状況を受けとめ、総括して次に移ってゆく。。。
悲しみ、そして「さようなら」と別れ、次に移る工程をきちんとこなすことが
未来の人々への思いやりだと思うのです。
今までの日本ではないのです。
けれど「さようであるならば」
私たちは、次の段階に進まなければなりません。
きちんと悲しんだ後で。
たくさん、泣いた後で。
※わたしは縁あって、この映画を微力ながら応援させていただいています。
太田監督の対談が上映前後に催されていますが、
ここに、作家山川健一さんとの対談をアップしたものを張らせていただきます。
とても深いお話です。
わたしは10年ほど前に両親を相次いで亡くしました。
あまりにも悲しい出来事であったはずなのに、なぜか想像をしていた程泣けなかったのです。
きっとまだ緊張が続いているのだ、疲れているのだと自己分析しながらも、
次第に 、このままでは精神的に参ってしまうのではないかという不安感に襲われ、
もともと興味を持っていた精神世界へ足を踏み入れていきました。
それがヨガでした。
学んでゆくにつれ、明るい光を求め始めたのですが、
どん底に突き落とされるような感覚に何度も陥りました。
その辺りだと思います。
両親が本当にこの世にいないのだと思えるようになったのは。
「あぁ、話したいなぁ」と思っては、胃の辺りがキュっとなる苦しい淋しさを味わえるようになったのは...
そして、やっと両親への感謝の気持ちがわいてきたのです。
光を探すには暗闇が必要だと知りました。
わたしは両親の死を受け入れてはいなかったから、泣くことができなかったのです。
当たり前のことをもっともらしく書いていて、なんとも滑稽ですが、
悲しみを、ありのまま受け入れるということほど、私たちが不得意としているものはないかもしれないと
原発事故以降は特に実感しています。それは今も継続中ですが...
もともとチェルノブイリ原発事故に恐怖を抱いた青春時代があったので
それがこの日本で起こったことを知った瞬間は、頭が真っ白になりました。
しかし、周囲はまるでのんきに過ごしているようにみえ、
「テレビでそんなに言ってないから、大丈夫なんでしょ?」という反応を聞く度に
得体のしれない恐怖がわいてきて、孤独感を募らせる毎日でした。
それからは周囲の方が、わたしを遠巻きにするほど様々な情報を得ることに必死になっていました。
つのりゆく政府の対応への不信感、この世の中の、世界の原発構造への憤り、、、
そして、、、もちろん、福島の方々への想像をできる限りめぐらせてきたつもりです。
しかし、それは甘かった。
映画「朝日のあたる家」の冒頭から、わたしは終始泣き通しでした。
こんなに泣いたことはないです。
様々な種類の涙でした。
実はわたしは「泣ける映画」と謳った映画には全く興味がありません。
それほど「泣かされる」ことが嫌いなのです。
この映画は、泣かそうと工夫された場面はおそらくどこにもないのです。
ただただ淡々と、原発事故のあの日から起こった出来事が描かれているだけですから。
しかし、わたしは涙が止まりませんでした。
そしてそれは想像をしてもしきれない、私たちが味わったことのない
全く違った種類の「悲しみ」だと感じました。
この国は、いったいどこへ行こうとしているのだろうと思います。
「悲しみ」を置き去りにして。
光が暗闇の中でしか見いだせないとしたら、
私たちは、まず、この暗闇を見つめなければならないと思います。
きちんと悲しむことをしなければ、先へ進めないと思うのです。
いや、進んではいけないと思います。
映画冒頭に映し出された富士山に、わたしは突然涙が溢れました。
その切ないほど優雅で美しい姿に、心の底から申し訳ない気持ちになりました。
そして、なぜか「さようなら」という言葉が浮かびました。
日本語の「さようなら」は、
「さようであるならば」(そうならなければならないならば)というのが語源といいます。
これまでの状況を受けとめ、総括して次に移ってゆく。。。
悲しみ、そして「さようなら」と別れ、次に移る工程をきちんとこなすことが
未来の人々への思いやりだと思うのです。
今までの日本ではないのです。
けれど「さようであるならば」
私たちは、次の段階に進まなければなりません。
きちんと悲しんだ後で。
たくさん、泣いた後で。
※わたしは縁あって、この映画を微力ながら応援させていただいています。
太田監督の対談が上映前後に催されていますが、
ここに、作家山川健一さんとの対談をアップしたものを張らせていただきます。
とても深いお話です。
Posted by 見廻りくま at 14:19│Comments(0)
│皆さんの感想等
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。