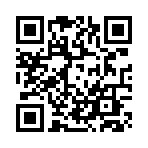2013年12月22日
「朝日のあたる家ーはシュミレーション映画だ」という支配人?(4)

「朝日のあたる家」で描かれる物語。
地震が起こり、原発で爆発、官房長官の会見があり、
避難、仮設住宅、一時帰宅と
原発事故の展開をリアルに描いてあるのだが
それらのほとんどは福島で起こった事実である。
それを映画では同じ展開で、同じ時間に地震が起こり、官房長官会見があり、と
同じ時間軸で描いている。
さらに、官房長官、御用学者の台詞も当時とまんまにした。
一字一句。現実の彼らと同じことを話している。
と書くとこういう人が出てくる。
「そこまでするなら、なぜ、福島を舞台にしないの?」
それこそ「再現ドラマ」意味がないのだ。
福島を舞台にすると、観客はこう感じる。
「こんなことがあったのか....福島大変だったなあ~」
でも、それは他人事。今の風潮と同じ。
自分のこととして考えていない。
だから、舞台を静岡県に移し、311以降の物語とした。
ロケ地である湖西市は日本の原風景が残る素敵な町
その風景を観ていると、こう思えてくる。
「うちの田舎に似ているなあ」「昔はうちの町もこうだったなあ」
そして、知らないうちに自分の町で、自分の古里で原発事故が起こると
こうなるんだろうなあ......という視点で物語を観ていく。
主人公の平田家は4人家族だが、気づくと観客であるあなたが
5人目の家族となり、原発事故を体験することになる。
つまり、福島の原発事故が自分の住む町で起こったら?
という体験をするのである。
だから、人が死ななくても悲しみは溢れるし、
押さえようない苦しみや怒りがこみ上げる。
これを所謂「再現ドラマ」にすると、他人事となり「福島大変だったなあ」で終わるし
「シュミレーションドラマ」にすると、
「へーー原発事故って大変だなあ」
とは思ってもリアリティは感じない。
いずれのドラマにもいえることは、自分とは関係のない事件に見える。
見終わったらすぐに忘れる。
そもそも、近未来を描いたシュミレーションドラマを観て、涙がこぼれることはない。
いくら「東京は津波に教われる!」といわれても「ふーーーん」と思う人が多数。
同じ手法で福島の原発事故を描いていも
別の町でシュミレーションして描いても、
「悲しみ」や「恐怖」を伝えることはできない。
だからこそ、「シュミレーションドラマ」でも「再現ドラマ」でもない
(それらで「朝日の」物語は描くことはできない)
新しいスタイルを作り出し描いたのである。
(つづく)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。