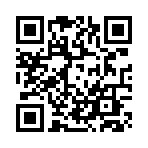2015年05月31日
映画「向日葵の丘 1983年夏」はどんな映画?

パソコンも、携帯も、DVDもない30年が舞台。
マイケル・ジャクソンの「スリラー」が流行り、松田聖子と中森明菜が人気
レンタルレコードが増えて、ビデオデッキが普及し出したころ
バブル景気直前の田舎町。高校時代を過ごしたあの日

涙と感動の中に、あなたが忘れていたものが見つかる。
この夏いちばん泣ける映画。
出演 常盤貴子、田中美里、藤田朋子
8月22日(土)品川プリンスシネマで先行公開

2015年05月29日
「朝日のあたる家」報道の中立公正なんてあり得ない! 偏った報道こそ意味がある?

このところ、報道の中立公正についての意見をよく見かける。報道するときは客観的に、冷静に、伝えることが大事。偏った見方をしたり、一方的な伝え方をするべきではない。といわれる。が、果たしてそうだろうか? 昔から引っかかっていたのだが、最近特にそのことがいわれる。Facebookを読んでいても「客観的報道をしろ」とか「報道で意見はいりません」とか書く人がよくいる。
しかし、そもそも、客観的な報道なんて出来るものなのか? 例えば公害問題を記事にするとき、その記者が子供の頃に公害で苦しんでいたら、どーしても批判的な記事を書く。だが、公害問題に悩まされたことがなく、日本のためには経済復興こそが大事と願う記者であれば、「必要悪」と考えるかもしれない。
その時点でもう公正中立ではなくなっている。全ての事柄に利害関係や思想がなく、客観的に見ることのできる人なんているだろうか? 何より日本という国に住み、そこで育つだけで、日本的な価値観を持ってしまう。そんな記者が価値観の違う他の国のことを客観的に見れるのだろうか?
外側から見れば許せない事件でも、内側から関係者からすれば悲しい事情のある仕方ない事件だったりする。それを客観的に見たことだけを伝えて、事情の分からぬ視聴者が「許せない」と思うだけの報道に問題はないのか?

その事件なりに踏み込めば、もう客観的な報道などできなくなる。被害者の気持ち。加害者の事情。それを客観的に伝えられるだろうか? どうしても一般の人は被害者に同情する。加害者を責める。だから、報道もすぐに「凶悪な犯人」「哀れな犠牲者」の構図で伝える。が、もうその段階で中立公正ではない。そもそも公正中立なんて不可能なのだ。では、どうすればいいのか?
意見を述べること。記者が意見を書くこと。日本の新聞は記者名を明記しないことが多いが、署名で記事を書くこと。自分が見た事件、現実をどう思ったのか?を伝える。自分の視点で伝える。酷いのか? 許せないのか? 悲しいのか? 感動したのか? 笑ったのか? 泣いたのか? どうするべきと考えたか? 何が問題だと感じたのか? 自分が見たことを自分の考えてと共に伝える。
「そんなことをすると感情的になり事実が歪められ、真実が伝わらない」という人もいるが、今の時代。報道メディアは1社ではない。いくつもある。テレビ、新聞、雑誌、ネット。さまさまなメディアが事件を取材する。当然、いろんな意見が出る。それを読み比べることで、真実はどこにあるか? 自分で考えるのだ。
「このAさんという記者は公害問題に怒りを感じているから、この記事も少し感情的だな」「Bさんはいつも鋭い記事を書くが、E新聞のこの意見が今回は正解ではないか?」とか比較することで、真実が見えて来る。つまり、ある法案審議を例にとれば「私は賛成です。なぜなら」「僕は反対です。これは危険過ぎる」と意見をいう方が、違いが出て、客観的に報道より比較しやすく、分かりやすくなるのだ。
実際、リテラシーのある人はすでに、報道をそういう形で受け取っているだろう。「A新聞は政府よりだから、政府に都合のいい意見をいうだろう」「Bテレビは反米だから、アメリカ批判が入っているな」とか「週刊Cは大手企業がスポンサーだから、国民より企業を優先しているな」という理解の仕方をしている。

だが、多くの人は今も「テレビが言っているから正しい。新聞に書いてあるから真実だ」と思っている。そして意見をいう報道機関があれば「偏向報道だ」「公正中立にやれ」と怒るが、日本人のいう公正中立というのは、外面だけを伝えるものであり、それでは真実は見えて来ない。また、非常にダマされやすいことにもなる。
アメリカのニュースキャスター。多くは自分の意見をいう。が、日本はキャスターシステムを取り入れたのに、意見をいうと「私見を挟むな」と批判する視聴者がいる。意見を言わないのはアナウンサーであり、キャスターは意見をいう存在なのである。「公正中立」をあれこれいう人の多くは、その辺も分かっていないことが多い。
これからの時代。大切なのはそれぞれが意見を持つこと。発言することだと考える。意見が違えば、そこから考えることができる。が、中立公正などというと、それが真実だと思い込み。意見が出て来ない。つまり、客観的報道というのは、視聴者や読者に考えるきっかけを持たせない危険性がある。
中立公正といい、本当に大切なことを見えなくして、一部の人が都合のいい政策を進めてしまう。なのに視聴者自身が「公正中立」と叫ぶ姿は、誰かの思う壷だと感じてしまう。

2015年05月29日
2015年05月28日
「朝日のあたる家」報道の中立公正なんてあり得ない! 偏った報道こそ意味がある?

このところ、報道の中立公正についての意見をよく見かける。報道するときは客観的に、冷静に、伝えることが大事。偏った見方をしたり、一方的な伝え方をするべきではない。といわれる。が、果たしてそうだろうか? 昔から引っかかっていたのだが、最近特にそのことがいわれる。Facebookを読んでいても「客観的報道をしろ」とか「報道で意見はいりません」とか書く人がよくいる。
しかし、そもそも、客観的な報道なんて出来るものなのか? 例えば公害問題を記事にするとき、その記者が子供の頃に公害で苦しんでいたら、どーしても批判的な記事を書く。だが、公害問題に悩まされたことがなく、日本のためには経済復興こそが大事と願う記者であれば、「必要悪」と考えるかもしれない。
その時点でもう公正中立ではなくなっている。全ての事柄に利害関係や思想がなく、客観的に見ることのできる人なんているだろうか? 何より日本という国に住み、そこで育つだけで、日本的な価値観を持ってしまう。そんな記者が価値観の違う他の国のことを客観的に見れるのだろうか?
外側から見れば許せない事件でも、内側から関係者からすれば悲しい事情のある仕方ない事件だったりする。それを客観的に見たことだけを伝えて、事情の分からぬ視聴者が「許せない」と思うだけの報道に問題はないのか?

その事件なりに踏み込めば、もう客観的な報道などできなくなる。被害者の気持ち。加害者の事情。それを客観的に伝えられるだろうか? どうしても一般の人は被害者に同情する。加害者を責める。だから、報道もすぐに「凶悪な犯人」「哀れな犠牲者」の構図で伝える。が、もうその段階で中立公正ではない。そもそも公正中立なんて不可能なのだ。では、どうすればいいのか?
意見を述べること。記者が意見を書くこと。日本の新聞は記者名を明記しないことが多いが、署名で記事を書くこと。自分が見た事件、現実をどう思ったのか?を伝える。自分の視点で伝える。酷いのか? 許せないのか? 悲しいのか? 感動したのか? 笑ったのか? 泣いたのか? どうするべきと考えたか? 何が問題だと感じたのか? 自分が見たことを自分の考えてと共に伝える。
「そんなことをすると感情的になり事実が歪められ、真実が伝わらない」という人もいるが、今の時代。報道メディアは1社ではない。いくつもある。テレビ、新聞、雑誌、ネット。さまさまなメディアが事件を取材する。当然、いろんな意見が出る。それを読み比べることで、真実はどこにあるか? 自分で考えるのだ。
「このAさんという記者は公害問題に怒りを感じているから、この記事も少し感情的だな」「Bさんはいつも鋭い記事を書くが、E新聞のこの意見が今回は正解ではないか?」とか比較することで、真実が見えて来る。つまり、ある法案審議を例にとれば「私は賛成です。なぜなら」「僕は反対です。これは危険過ぎる」と意見をいう方が、違いが出て、客観的に報道より比較しやすく、分かりやすくなるのだ。
実際、リテラシーのある人はすでに、報道をそういう形で受け取っているだろう。「A新聞は政府よりだから、政府に都合のいい意見をいうだろう」「Bテレビは反米だから、アメリカ批判が入っているな」とか「週刊Cは大手企業がスポンサーだから、国民より企業を優先しているな」という理解の仕方をしている。

だが、多くの人は今も「テレビが言っているから正しい。新聞に書いてあるから真実だ」と思っている。そして意見をいう報道機関があれば「偏向報道だ」「公正中立にやれ」と怒るが、日本人のいう公正中立というのは、外面だけを伝えるものであり、それでは真実は見えて来ない。また、非常にダマされやすいことにもなる。
アメリカのニュースキャスター。多くは自分の意見をいう。が、日本はキャスターシステムを取り入れたのに、意見をいうと「私見を挟むな」と批判する視聴者がいる。意見を言わないのはアナウンサーであり、キャスターは意見をいう存在なのである。「公正中立」をあれこれいう人の多くは、その辺も分かっていないことが多い。
これからの時代。大切なのはそれぞれが意見を持つこと。発言することだと考える。意見が違えば、そこから考えることができる。が、中立公正などというと、それが真実だと思い込み。意見が出て来ない。つまり、客観的報道というのは、視聴者や読者に考えるきっかけを持たせない危険性がある。
中立公正といい、本当に大切なことを見えなくして、一部の人が都合のいい政策を進めてしまう。なのに視聴者自身が「公正中立」と叫ぶ姿は、誰かの思う壷だと感じてしまう。

2015年05月28日
「朝日のあたる家」インドネシアとカナダで上映会準備中!

映画「朝日のあたる家」劇場公開が終了。
平行して進めて来た海外上映
すでにロスアンゼルス、シンガポール、ドイツ、ニュージーランド、アリゾナで上映されたが、
現在、インドネシアとカナダでの準備が進んでいる。
詳細が決まり次第また告知する。

2015年05月28日
「朝日のあたる家」嫌われてこそ映画監督? 「いい人」と呼ばれる奴は駄作しか撮れない?

知り合いの製作会社にいくと、よく他の監督のうわさ話を聞く。「A監督の新作、惨敗らしいよ。この間も、客が2−3人。厳しい〜。A監督、ほんといい人なのにな。がんばってほしいよねえ」
逆にこんな話も聞く。「B監督とはもう仕事することはないなあ〜。あそこまでわがままだと付き合いきれない。もう少し、チームワークとか考えないと、誰も相手にしてくれなくなるなあ」
こう聞くと、A監督はいい人だが、新作がヒットせず苦戦しており、同情を集め、応援したいという状況。比べてB監督は身勝手で嫌われている。離れて行く人が多く、存亡の危機にある。という印象を持つだろう。が、ここで抜けている情報がある。B監督の映画はヒットしているのか?というのが分からない。
実はH監督の作品は毎回ヒットしている。比べてA監督は毎回惨敗。どういうことなのか? 何度も記事を書いて来たが、その背景に映画界的な事情があるのだ。A監督。いい人で、製作会社が「この女優で行きましょう! テレビドラマのレギュラーも決まったし」というと「じゃあ、その子で行きましょう」と従う。
が、B監督は「その子じゃ無理、シナリオのイメージと違う!」ということを聞かない。一事が万事、A監督は皆と協調し、仕事をする。B監督は全てを自分で決め、人のいうことを無視。こう書くと、「仕事なんだから、やはり協調性が大事。A監督はそれを理解しているが、B監督は常識がない」と思う人もいるだろう。
しかし、映画というのは皆の意見を取り入れて、全員が満足する形で進めるといいものができない。1人の作家がやりたいようにやったときに、名作と呼ばれる作品が生まれたりする。黒澤明だって、キューブリックだってそう。巨匠と呼ばれる監督は皆、完全主義者で我がままで、誰も止めることができない。その意味でいうと、皆のいうことに従うA監督にいい作品が作れないのも当然。
さらに、製作会社というのはご存知の通り。いかに製作費を抜き、自社の利益にするか?としか考えないところが多い。いい映画を作ろう!と思ってる社は少ない。そして、面倒なことはしたがらない。さらに、自社と癒着した芸能プロダクションの俳優をキャスティングすることで、キックバックをもらったり。いざというとき大物俳優を都合してもらうときのための恩を売りたい。というようなことばかり考えている。
なのに、監督が「この俳優はダメだ」というと、キックバックももらえないし、恩も売れない。撮影も適当にやれば、そこそこで終わるが、熱を入れてがんばられるといろいろ面倒。つまり、製作会社にとって「いい監督」というのは、自分たちの言うことを聞き、面倒なことをせず、不正や癒着に目をつぶる人たちのことなのだ。だから、「A監督はいい人だ」というのだ。
それに対してB監督が嫌われるのは、本当にいいものを作ろうとして妥協せず、無理をして、努力をするから、会社としては面倒くさい。いつも以上の労力を強いられる。自分たちのいうことを聞かない。不正や癒着ができない嫌な奴なのだ。だからこういう。
「B監督とはもう仕事することはないなあ〜。あそこまでわがままだと付き合いきれない。もう少し、チームワークとか考えないと、誰も相手にしてくれなくなるなあ」
製作会社のいう本当に意味が分かってもらえたと思う。僕も人の意見を聞かず、絶対に自分を曲げない方だから、製作会社とはよくぶつかった。一度やったところは二度と声をかけてくれなかった。プロデュサーはあちこちで悪口をいいまわっているようだ。が、まだまだ、悪評を聞くことは少ない。むしろ「太田はよくやっている」という話を聞く。これはまだまだ我がままが足りないということだ。
映画監督というのは、嫌われている人ほどいい映画を作る。「いい人だ」と言われてる人ほど、ろくでもない映画を作っている。不思議な世界ではあるが、事情を知れば「なるほどそうだな!」と思ってもらえただろう。

2015年05月28日
「朝日のあたる家」ウッディ・アレンが人嫌いになった理由を感じる日々

ハリウッド俳優のウッディ・アレンはインタビュー嫌いで有名だ。というより「人嫌い」と言われている。パーティや記者会見にも出席しない。人前に現れることがまずない。ニューヨーク生まれのニューヨーク育ち。多くの人に愛されるアクターであり映画監督。なのになぜ、人嫌い?と思っていたのだが、「もしかしたら、こういうことかな...」と思えること。この数年、続いている。
撮影や宣伝でお世話になった地方の方々の多くは、その後もお付き合いが続き、その街では撮影しない僕の新作も応援、支援してくれる。本当に感激。なので、別の仕事であっても、その人たちの街を通るときには、途中下車してお訪ねし、ご挨拶したり近況報告したりする。
東京に戻るときにお世話になったA市で途中下車。地元の方に新作映画の進展報告等をすることがある。が、お世話になったB市が近所にある。A市に寄ったことを知ると「監督。B市にも寄ってくださいよ。寂しいなあ〜」と言われる。でも、両方の街に寄る時間はなく、考えた末に短時間で何人も訪ねることができるA市を申し訳なく思いながら選んだのだ。

また、お世話になったC市の方をお訪ねしたときはこう言われた。「ここまで来たのなら、少し先のD市まで行った方がいい。皆、喜んでくれるよ」確かにその通りだ。が、C市でさえかなり無理して来ている。D市まで行くと、その日の内に東京に戻れない。残念だが行けないと伝えると「でも、あの街でもお世話になったんでしょう? 感謝の気持ちが足りないじゃない〜」と注意される。
無理してお訪ねしても、結果、そんなふうになることがある。また、訪ねた街でも、こう言われる。「***さんと、***さんを訪ねたそうですね? 何でうちには来てくれなかったんです?」訪ねるときも、いろいろ考える。自宅だといきなり行くのは失礼。
なので、お店をやっている方。会社を経営している方で、急に訪ねても、対応してもらえ、迷惑がかからない方を選んでお訪ねする。それでも「うちへは来てもらえなかった...」と言われる。1人訪ねると「なんで**さんだけ」「何でA市だけ」「だったらC市も!」と不満を持つ人が出てくる。
ある街ではお訪ねすると、誰かが「監督が来てるよー」といろんな人に連絡をしてくれて、決まったお店に集合してくれる。これは一度に多くの人にご挨拶ができる上に、来れる人は来て、都合の悪い人は来ないで済む。不公平も生まれにくく、ありがたかった。街の方々は毎回、歓待してくれて、撮影時の思いで話に花が咲く。

でも、あるとき、その会を終えて東京に戻ると、その中のお1人からメールが来ていた。「今後、来るときは1週間前くらいに事前に連絡してください。急に来て招集されても迷惑です。こちらにも生活がありますので」と。それなら欠席してくれてもいいのだが.....お会いしたときは笑顔で対応してくれたのに、実は迷惑だったと分かり。心が沈んだ。
ただ、僕も1週間前に予定を立て、その街にお寄りするという形は取れない。監督業はご存知のようにブラック企業を超える仕事量。スケジュールも突然変わる。帰京予定日が変わったり、現地に予定以上に滞在したりもする。そんな中で帰京途中。「あ、今日なら**市で途中下車できる。明日、東京に着けば仕事にも影響しない。きっと喜んでくれるだろう」と、その街を訪ねる。
けど、地元の方も急に来られては困る方がいるという現実。笑顔で迎えてくれても内心は迷惑。他の方々も笑顔で接してくれるが、実は「急に来られてもなあ〜」と思いながら我慢していたのではないか? ある街を訪ねると、他の街から不満が出る。「D街も行くべきだ」と注意される。もちろん、本当に喜んでくれている人たちも多いだろう。でも、次第に分からなくなってくる。
それに、地元の方の要望を全て受け入れることはできない。本業に大きな影響が出てしまう。一部の声だけ受け入れても、また別のところから不満の声が上がる。何をしても、良かれと思っても、誰かが嫌な思いをする。誰が悪いということではないのに、歯車がどんどん噛み合なくなっていくような、悲しさを感じる。
そんなとき、ウッディ・アレンの話を思い出した。もちろん、彼は大スターで僕なんかは今も無名の監督。同じレベルでは語れないが、アル・パチーノも、ロバート・デ・ニーロも、ウオーレン・ベティも、人嫌いと言われているたぶん、僕が体験したことの数百倍も何千倍ものことを経験したのではないか? 良かれと思ってしたことが、応援している人を傷付けたり.....対応できない要望が次々に来たり。やがて人に会うことさえ嫌になり、インタビューにも答えなくなった...........そんなことを考えてしまう。

2015年05月28日
新作「向日葵の丘」大阪、名古屋でも公開決定!!!!!

「朝日のあたる家」に続く、僕の新作「向日葵の丘 1983年・夏」
お待たせしました。
東京に続き、大阪と名古屋の映画館でも


公開されることになりました。
大阪はシネリーブル梅田、布施ラインシネマ
名古屋は伏見ミリオン座
いずれも大都市の素敵な映画館。
詳細は追って発表。まずは、報告まで、
しかし、これは凄いぜよ! シェアよろしくお願いします。

2015年05月28日
「朝日のあたる家」自分の価値観を押し付ける人たち。なぜ、人はそれぞれ違うことを認めないのか?

映画撮影を終えると、お世話になった方々に挨拶まわりをする。本来、それは監督の仕事ではなく、製作担当がするのだが、僕の場合はスタッフが集まる前に、1人でロケ地に乗り込み。いろんな人を訪ね、応援を求める。そんなことを1−2年続ける。だから、本来、製作担当が行くべき挨拶まわり。僕も同行する。感謝の気持ちと無事撮影終了を伝えるためだ。ただ、スタッフから言われる。
「本来、それは製作担当がやるべきこと。監督は早く東京に戻り、編集作業を始めるべき。そして少しでも早く完成させて、応援してもらった人たちに見てもらうことこそが大事。最初は監督と出会ったことで、応援してくれた方々でも、その後、製作担当に引き継がれた仕事。それを監督が何十人もの人を何日もかけて訪ねるのはどうか? 建築業でも、ビルを建てたからと、社長が関係者を訪ね挨拶をしてまわったりはしない。それは現場担当がやるじゃないですか?」
確かに、その通りだ。が、僕は1人1人の顔も名前を知っているし、何度もごちそうになったり、いろんなことを教えてもらったりしたので、感謝の気持ちを伝えたくて、お礼参り(?)をしているのだ。が、何カ所かの地域で映画を作りをすると、あれ?と思うことも出て来た。
ある街での撮影後、いつものように地元の方と製作担当と、僕の3人でお礼参りツアーをした。その中で、あるお弁当工場を訪ねることになる。そこは大量のお弁当をもの凄く安い値段で提供してくれた。お礼を言わなければならない。

そのとき地元の方はいった。「俳優やスタッフ全員でお礼に伺いましょう。監督と製作担当さんだけでは失礼です」ん?ちょっと待ってください。弁当を扱うのは製作担当。だから、本来は彼のみが挨拶に行く。僕も本来なら行かない。が、その工場の社長とは何度かお会いしているし、感謝の気持ちを伝えたかった。なのに、地元の方はスタッフ&キャスト総出で行ってほしいという。
「俳優もスタッフも弁当を食べたんだから、お礼に行くのは当たり前だろ!」
何でそうなるのか? まず、映画の世界では、俳優&スタッフに弁当を出すのは製作サイドとして当然のこと。それが映画界の決まり。ただ、製作担当者としては、超破格の値段にしてもらえたことで、製作費を節約大助かりだった。だから、製作担当者がお礼に行く。僕も感謝を伝える。
しかし、その地元の方の考えはこうだ。何かをごちそうになったら本人がお礼をいうべきだ。という一般的な発想なのだ。確かに、地元の家に呼ばれて、夕飯をごちそうになれば、呼ばれた客はお礼をいうのが当然。
ただ、映画撮影にその構図は当てはまらない。例えるなら、農家がある社員食堂に超破格で野菜を卸した。その食堂で社員が食事をした。お礼に行くのは社員食堂の担当者だ。食事をした社員はいつもと同じにご飯を食べただけ。なのに、社員も全員、お礼に行けというのと同じになる。
そして、もし、それを実行すれば、バスをチャーターして、1日スケジュールを空けて、皆でお弁当工場に行かねばならない。宿泊費も1日分プラス。当然、俳優事務所はクレームを付ける。なぜ、うちの俳優に挨拶まわりをさせる。
弁当を出すのは製作サイドの義務。演技以外のことをさせるなら、追加ギャラを寄越せというところも出てくる。結果、全員で行くことで、せっかく破格の値段にしてもらったのに、相当の出費をせねばならない。だったら、通常の業者から弁当を買った方が安上がり。

でも、その人は映画界の事情が分からない。できれば、先の社員食堂の構図を想像してくれればいいが、スタッフもキャストも皆、撮影隊のメンバーとひとくくり。全員でお礼をいいに行ってほしいと主張する。事情を説明すると、無理であることは理解してくれた。「じゃあ、監督と製作さんだけでいいよ」といい、彼は弁当工場の社長に平謝りしていた。
挨拶まわりを全て終えて、帰京しても、あとからクレームが来ることがある。「撮影終了から1ヶ月。なぜ、挨拶に来ない。あれだけ応援したのに失礼な!」と言われたこともある。なんで1ヶ月? と思ったのだが、その人の業界では1ヶ月後にあらためてお礼をするのが習わしなのだそうだ。
だが、こちらは編集の真っ最中。その上、製作担当はすでにプロジェクトを離れて、別の仕事をしている。おまけに、別の業界のしきたりを映画作りに押しつけられても困る。こちらは撮影終了。完成。公開。を区切りに挨拶に行っているのだ。そんなふうに先方には先方の習わしがあるのだが、それを映画作りにも当てはめて、怒られたことがある。
宗教の違いで戦争をする国がある。同じ反原発を訴えながら、些細な違いで互いを批判しあう人たちがいる。推進派を攻撃するなら分かるが、反原発を主張する同士が中傷し合う。どの分野も自分の価値観を絶対だと信じ、それを押し付けようとする。方法論が違えば、自分なりのやり方で進めばいい。違う相手を否定する必要はない。自分の価値観を相手に押し付ける必要はないのだ。
このFacebookでも、自分と意見が違うと長々と批判コメントして来る人がいるが、(或はダイレクトメッセージを送ってくる)それは自分のFacebookで書けばいいこと。なぜ、人は他人に意見や価値観を押し付けるのか? そんなことをときどき考えてしまう。

2015年05月23日
映画「朝日のあたる家」イベント上映 フィルムレンタル代の御案内

●上映料金
上映一回の基本料金
有料・無料不問50人以下の場合:50.000円(税別)
有料・無料不問100人以下の場合:100.000円(税別)
100人以上の場合は130.000円(税別)
※一回の上映で基本料金の2倍を超える入場収入がある場合、収入の50%を上映料とさせていただきます。
※同日に複数回の上映を行う場合は、1回につき上記金額の半額になります。
●上映素材
上映用の素材はブルーレイ・DVDがございます。会場の設備にあわせてお選びください。
●太田隆文監督の公演付き上映に関して
上映会で太田隆文監督の講演をご希望の方々のために講演依頼も受け付けております。
講演料は30.000円(交通費・宿泊費は別途)となります。
●上映素材の貸出と返却の方法
貸出・・日時に指定の無い場合は、上映の3日前まで発送いたします。
返却・・上映後に1週間以内に宅急便にてご返送下さい。尚、返送料はご負担ください。
●精算方法
請求書には、上映料金と宣伝素材物の料金を集計いたします。
請求書に記入されている指定の銀行口座にお振込みください。
●宣伝材料
以下の料金で販売しております。なお、送料は着払いでお願いしておりますのでご了承ください。
・B5サイズ下白チラシ6円(1枚)
・B2ポスター250円(1枚)
※独自にチラシを製作される場合などのために、写真素材を提供しております。
ご希望の方はお問い合わせください。
●物販
パンフレット1000円(1冊)
販売手数料として売上の10%を納めていただきます。
●申し込み方法
FAX・またはメールにて①上映日時、②会場、③集客予定人数、④講演の有無、⑤宣材物の有無
⑥申込者の連絡先を記入いただき以下までお問い合わせください。
●問い合わせ先
株式会社渋谷プロダクション 担当:小林
150-0042 東京都渋谷区宇田川町12-3ニュー渋谷コーポラス708号
TEL:03-5728-4080 FAX:03-5728-4081
メール:info(アット)shibuyapro.net
※(アット)を@に替えて送信ください。